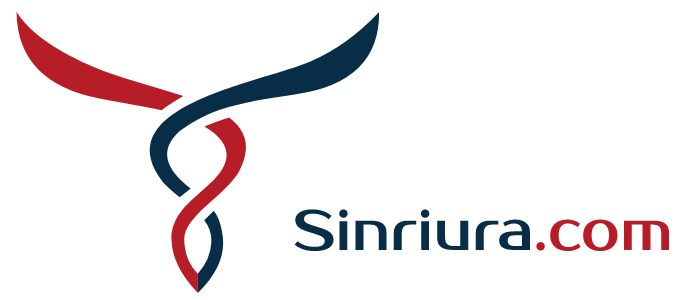精神分析の基本的な諸原則をはっきり規定することはむつかしい。精神分析はたんなる理論体系ではなく実証的な研究であり、まだ形成の途中にあるものだからである。その理論はたえず変化しつつある。したがって、精神分析の結論は一見決定的なものであるかのごとき印象を与えるときにも、常に多少は暫定的な部分を含んでいる。このことを前提として、以下に二、三の主な原則を説明することを試みよう。
精神分析によれば、精神は意識的なものだけではなく、むしろ意識的なものは精神の一部にすぎない。我々は精神の中におこることの一部しか自覚しないが、残りの無意識的な部分も意識的な部分と同様のものである。それは思考、要求、欲望、恐れ、希望などである。無意識的過程は、それが意識されていないということを除いては意識的過程と少しも異ならない。無意識的過程を勘定に入れて初めて精神活動はその意味が理解できるようになる。無意識を除外したら心的過程は頁をあちこちで引き裂かれた本のようなものである。人はそれを読むことができるし二、三の章節はよく理解できるが、その全体の意味は、読者が足りない部分を推察できない限り、理解できないか、またはなにか不完全だという印象を与える。
精神生活は葛藤に満ちている。人々はこれらの葛藤のうち、外部の環境との葛藤に重きをおく
傾きがあった。これに反し、精神分析は内的葛藤の豊富さを明らかにした。我々の本能、我々の動物性衝動の激しい活動に対して、我々はさまざまな方法で防御する。あるいは外部環境との不愉快な衝突を恐れて、本能を抑え、或いは良心の反対によって本能に対抗する。またときには本能によって我々自身の統制が失われ、我々の人格が破壊されるのではないかという危険を漠然と感じ、その本能から逃避することもある。精神分析は心的生活において次の三つの部分を区別する。第一に「エス」、つまり我々の本能的活動、第二に「自我」、すなわち我々の人格の組織化された部分、第三に「超自我」、これは大体道徳的良心に相当するものである。これらの部分からの矛盾した諸要求がたえず我々がどうにか解決しければならないところのさまざまの葛藤を作り出す。そして一つの葛藤の解決の試みが、再び新たな葛藤の解決の試みが、再び新たな葛藤を作り出すことも少なくない。神経症の症状やさまざまの性格の隔たりはこれらの葛藤の不完全な解決の結果である。
本能の性質やその発達の研究はエスの心理学と呼ばれ、自我と超自我の研究は自我の心理学と呼ばれる。精神分析以前にはすべての心理学は自我の心理学であり、しかも自我の外部にい向けられた面のみを研究した。これに反して精神分析的な自我の心理学は、自我を自我とエス、超自我および外界との関係において研究する。エスの本能の中に、フロイトは性的本能と攻撃的本能とを区別する。フロイトにとっては子孫の繁殖に役立つ本能だけが「性的」なのではない、彼はこの言葉をもっと広い意味での肉感性の意味に用いる。それは神学者の肉的なる欲望と同じ意味であり我々が日常生活でLOVEという動詞をつかう場合をすべて含んでいる。次に攻撃性とは憎悪、反抗、破壊などの本能を総括するものである。
自我の本能に対する闘争において理想的解決は、本能のうち、現実に適応し、良心が是認する部分にのみ満足を与え、多を拒絶することである。しかしこれは不快さを我慢できる人、精神分析的な用語で言えば「強い自我」のみがなしうることである。
その他に、内的緊張を軽減することはできるが、問題を解決することはできず、そのため種々の副作用を生む原因となるようなさまざまの防衛の方法がある。そのなかで最も重要なのは抑圧である。これはいわば逃げようとして、砂の中へ頭を突っ込む駝鳥のやり方である。本能の要求は意識の外に押し出され、欲求は無意識的になるがその力は失わない。例えば怪しい人物が召使から部屋の外へ追い出されても、地下室で悪事をたくらんでいる場合に似ている。実際、抑圧は自我統制とは全く別物である。後者においては我々は欲求の存在を自覚しその力を制圧している。抑圧においては、衝動は無意識的になるけれども 活発なままで存在する。のみならず抑圧された本能は自我の統制から離れ、それ自身の活動を続けるようになる。本能が抑圧されると、かえって自我による意識的統制が不可能になるなるのである。
抑圧という述語は今では日常語になっている。しかし他の多くの場合と同様に、この流行は誤解にもとずいている。日常語で抑圧という場合それはたいてい「意識的制御」の意味に用いられている。
さて、抑圧された本能は減弱することなく、再び表面に現れようとする。意識の領域から押し出された本能はしばしば偽装されて再び現れる、あたかも上に述べた怪しい人物が仮装して戻って来て召使の前に現れ、部屋の中へ入りこもうとするように、抑圧された本能は神経症の症状の中に形を変えて現れるのである。
葛藤にはいろいろの種類があるが、神経症の根底には必ず、上述した広い意味での性的衝動との葛藤がある。これは前提ではなく実験の結論である。神経症がなぜ性的原因によってくるかという問題に関しては仮説的なことしかいえないが、性的本能は現実に適応させ、制御するのがことに困難な本能であることは確かである。自然はその意図を安全に遂行するするために、性的領域に莫大なエネルギーを注ぎ込んだらしい。
性欲は思春期に初めて発現するものではない。それは初生児の時期から存在している。もちろん、小児の性欲は成人の性欲の特徴をすべて具えているわけではない。しかし広い意味での性欲の特徴、欲望、興奮身体的快感の追求などを示している。小児の性欲は初めは原始的なな形で現れ、やがて四ー五歳ごろに著名になり、いわば第一次の思春期を示すが、次いで「潜伏期」に入り、最後に真の思春期、生物学的成熟期が現れる。
神経症は幼児期、ことに三ー六歳頃にその原因がある。成熟期に達すると、正常な成人の自我は葛藤にあうと、よかれあしかれそれを解決し、どうにかして病的な状態にならないで済むことが多い。これに反して幼児期における解決できなかった葛藤は成人になってからもーつまずきのー基になる。一度足の骨折を起こした人は同じ場所に再び骨折を起こしやすいのと同じである。幼児期の自我はまだ弱いので、幼児は容易に神経症を起こす・たいていの場合、幼児は葛藤を適当に解決できず、原始的な防衛反応をきたしやすい。わずかなショックでも幼児期の神経症は発生しうるのである。
幼児時代は我々の性格を大きな力で規定している。我々は一見現在のみに生きているように思えるが、実は我々は過去の亡霊によってとりまがれているのである。人々は各々に固有な、ひとつの見えない世界をもちこの世界を現実世界に統合させているのである。個人の外界に対する反応はある程度まで、この見えない世界によって規定されている。我々が知覚する多様な外界の出来事も、その多くは我々の小児時代の経験による選択の結果である。
精神分析的治療法は、直接の暗示や指導を与えることなく、単なる解釈の助けによって病気を治そうとする。抑圧を取り去り、無意識を意識化させれば、人間は葛藤を再び、そして今度は正しい方法で解決する力を持っている。過去の出来事を意識内に取り戻し、その出来事の魔力を奪い、これをその正当な場所、つまり過去へ捨て去らねばならない。「かつては本能であったところのものを、自我に化すること」、これが精神分析の目的である。
神経症の不安
不安
実際には危険に遭遇したり、危険が迫っているときに恐怖感をいだくと同じように、なにか危険を感じ、心配する悩みの感情。しかし、不安の場合には、恐怖の場合のように実際に危険を感じさせる対象がなく、「自由に浮遊しる」といわれる。生理的には発汗、急速な呼吸、動悸、下痢などをともなう。不安は精神分析の理論ではもっとも重要な概念の一つになっている。対象喪失の不安、愛情喪失の不安、去勢不安、罪や超自我の不安などが考えられている。自我が正常に働いているときには、不安は無意識的な願望が意識的にならないように防衛的手段をこうじるためのシグナルの役目をしている。不安がシグナルの役目をすることができなくなると不安症状がつくられるに至る。
別の辞典には次のようにあります。たいへんですが、読みましょう。どういう風に、書かれているかをーーーーー
(自己存在を脅かす可能性のある破局や危険を漠然と予想することに伴う不快な気分のこと。)漠然とした不安が何かに焦点化され対象が明確になったものを(恐怖)。行動理論では、両者を明確に区別することはしない。一般的には恐怖が特定の脅威事態に直面した時に生じる刺激誘発型の情動であるのに対し、不安は予感。予期。懸念といった個人の認知機能に大きく依存した認知媒介型の情動であるといえる。また、不安は信号や手がかりを通じて本来の危険を現在に手繰り寄せることによって発生することから、時間的展望のなかにおいて生じる現象であり、本質的に未来志向的な情動であるといえる。不安についての見解を大別すれば、精神分析的不安論、行動理論的不安論、認知論的不安論の三つに分けることが出来る。
①精神分析的不安論、フロイトは、脅威の原因が実際の外界にあるか、あくまで個人の内的衝動にあるかによって、現実不安と神経症的不安を区別した。現実不安が外的脅威によって予想される危害や苦痛に対する複合した内的反応であるのに対し、神経症的不安は不安を引き起こしている原因が内的衝動であるため、周回からわかりにくいという特徴がある。しかも、内的衝動の多くは抑圧されているため、不安を感じている当人にも不安の原因がわからないことが多い。
②衝動論的不安、行動理論的にみれば、不安も恐怖も本質的な違いはない。マウラーやミラーによれば、不安や恐怖は苦痛に条件づけられた反応と見なされている。特定の場面で苦痛を経験すると、その経験場面に含まれていた各種の刺激は、その後、実際の苦痛によって引き起こされたと同様な情動や回避反応を引き起こすようになる。そのように不安は、経験のなかに含まれていた刺激によって喚起され、反応と考えられる。また、回避条件づけにおいては、不安が脅威刺激の出現を妨げるような反応の動因になっている点も見逃すわけにはいかない。
③認知不安論、ラザラスは、不安が事態を驚異的だと認知することにより認知媒介型の情動でであると主張し、一時的評定、二次的評定、再評定の三つの認知的評定が関連していると考えている。一時的評定とは、予想される脅威事態の属性および自己関連性の評定である。二次的評定は脅威事態に対する制御可能性の経験から認知的評定に変更を加えることである。予想される事態が驚異的で自己関連性が高く、しかも、自分ではどうにも制御できないと評価したしたとき、不安は高くなると考えられる。
不安発生の条件としては、一時的過剰刺激、認知的不協和、反応の非有効性の三つに集約できる。一時的過剰刺激とは、恐れや不安が引き起こされる基本的原因となる強い感覚刺激のことである。耐性の限界を超えた刺激量は、高い情動覚醒を引き起こし、落ち着きのなさやさまざまな行動的変調を誘発しやすい。未知の事態に直面した時などにみられるもので、自分の解釈図式では自己と環境条件との関係を正しく定位できないことへの懸念と関係している。反応の非有効性とは、脅威事態からの回避や逃避を可能にしたり、高まった情動覚醒を低減させたりする反応が、不可能もしくは困難であることを意味する概念である。これらの条件は、客観的な条件というより多分に主観的なものであり、個人の認知機能によって不安の程度は大きく左右されることになる。
これ等の不安状態像は自分は多いに悩まされ、疲れはてている訳です。どれをとっても不安な様子は、さすがに参ります。
では、ここからの正常な状態はどうすればいいのでしょうか。と問いが出てきます。そう簡単にはいきません。説得やなぐさめはききめがありません。薬は、まあききめがある訳でなく、ひと休止になれば、いいかもしれませんが、有好とは思えません。