もう限界…家族の人格障害に振り回されるときの対処法
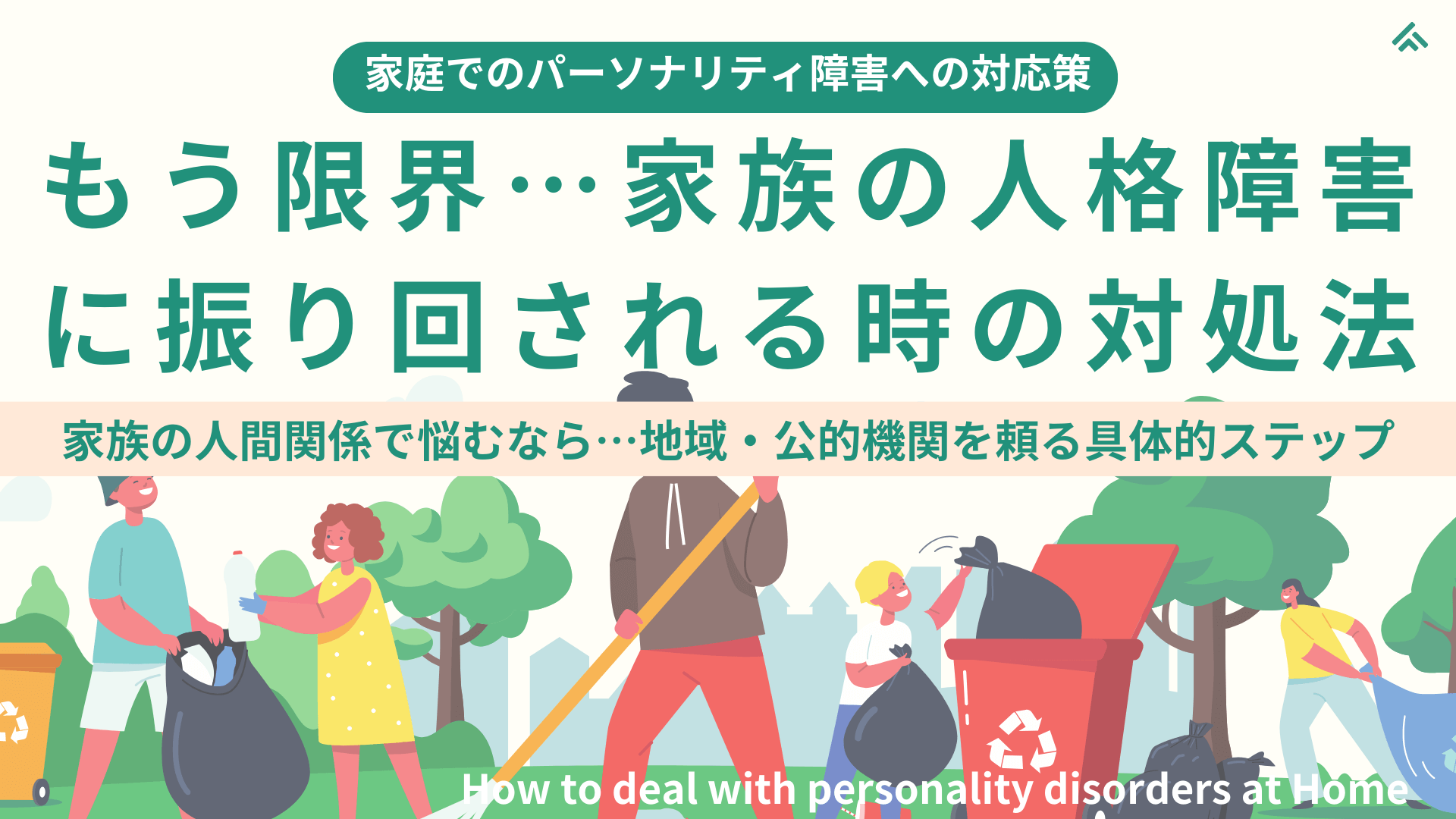
家族のパーソナリティ障害で悩むなら…地域・公的機関を頼る具体的ステップ
「家族の問題だから、何とか自分たちだけで解決しなくちゃいけない」——もしそんなふうに苦しんでいるなら、少しだけ立ち止まってみてください。人格障害(パーソナリティ障害)の特性を持つ家族との問題は、あなた一人で抱えるにはあまりにも大きいものかもしれません。愛情や責任感があるからこそ、周りに知られたくない、迷惑をかけたくないと思ってしまう気持ちは痛いほどわかります。
けれど、あなたの人生や心身の健康まで犠牲にしてしまえば、家族関係の修復さえ難しくなってしまいます。実は、地域コミュニティや公的機関には思っている以上に多様なサポートが存在しています。この記事では、「どのように地域とつながればいいのか」「具体的にどんな支援が得られるのか」をわかりやすく解説しています。つらい状況を変えるための第一歩として、どうかひとりで抱え込まず、少しだけ勇気を出して周囲の力を頼ってみませんか? あなたの行動が、家族全員にとって大切な支えになるかもしれません。
愛知県名古屋市の心理カウンセラー 浦光一
人格障害の家族がいるとき、なぜ地域やコミュニティに目を向ける必要があるのか
「家族の問題は家族で解決すべき」という考えが日本には根強くあります。しかし、人格障害の特性を持つ家族との問題は、しばしば当事者だけでは解決が難しいものです。日常の家事・育児・介護といったタスクに加え、相手の攻撃的・依存的・自己中心的な言動に日々振り回されていれば、家族のメンタルや体力が限界を超えるのも時間の問題。そこで大切なのが、地域社会やコミュニティと連携し、必要な助けを得ることです。
夫婦だけで抱え、共倒れしかけたケース【具体的な事例】
Aさん(妻)は、夫(自己愛性パーソナリティ障害かもしれない)の過度な要求に振り回され続けました。「俺様の言うとおりに動かないなら離婚だ」と常に脅され、妻が少しでも反論しようものなら激昂。Aさんは家事と育児とパート仕事を一手に引き受け、夫の顔色をうかがう日々。最初は「家族の問題だから、誰にも言わずに頑張らなきゃ」と思っていましたが、ある日ついに体調を崩し、うつ状態に。パート先にも行けなくなり、家の中はさらに混乱。夫は「使えない女だ」と罵声を浴びせ、子どもは「お母さんが倒れたらどうなるの?」と不安に陥りました。
このときAさんは、偶然知人から「市役所の○○課に行ってみたら?」「DV相談窓口とか、女性センターとかあるよ」と言われ、半信半疑で相談に訪れました。すると、想像以上に親身になって話を聞いてもらえ、無料の法律相談やカウンセリング機関を紹介され、さらには「地元の子育て支援グループ」や「夫婦問題サポート団体」の情報も得ることができたそうです。その後Aさんは、地域の支援者や同じ悩みを持つ人との交流を通じて、「自分だけが苦しんでいるわけではない」「必要なら法的措置もあるんだ」と知り、精神的に少しずつ回復。「夫が変わるかどうかはわからないけど、私は自分の生活を守るために動いていいんだ」という心の支えを得られました。
※本記事で紹介している事例は、いずれもプライバシーを最優先に考慮し、個人が特定されないように配慮したうえで掲載しています。具体的には、当事者の同意を得たうえで、一部の属性や背景を変更したり、複数のケースを参考にして再構成したりすることで、個人や企業を特定できないように工夫しています。読者の皆さまが安心して事例に触れられるよう、守秘義務とプライバシー保護を徹底して取り組んでおりますので、安心してお読みいただければ幸いです。
1. 地域コミュニティとのつながりをつくる
近所の自治会やサークルへの参加
「自治会とか、近所付き合いは苦手」という方もいるかもしれませんが、地域コミュニティには、意外と使える情報や人脈が転がっているものです。たとえば、
-
子育てサークルや PTA 活動
- 子どもがいる場合、同年代の子を持つ親同士で悩みを共有しやすい。表面的な話から始めても、少しずつ「実は家でこんな問題があって…」と打ち明けると、思いがけず「うちも似たような感じ」と共感してもらえるかもしれません。
-
スポーツや趣味のサークル
- ヨガ教室や音楽教室、町内のウォーキングクラブなど。ここで知り合った人から、地元の相談窓口や支援グループを紹介されることも。
ウォーキングクラブで救われた母親【具体的な事例】
Bさん(40代女性)は、娘(境界性パーソナリティ障害の傾向あり)の夜中の絶叫に悩まされ、精神的にも疲弊していました。家に閉じこもりがちだったものの、思い切って近所のウォーキングクラブに参加。そこで偶然、同じように「子どもが攻撃的で困っている」という人と出会い、話をするうちに「市内に家族会があるよ」と教えられました。Bさんは「まさかこんな近場で同じ境遇の人がいるなんて」と驚きつつ、家族会に参加して話を聞いてもらえたことで、大きな安心とヒントを得られたそうです。
※本記事で紹介している事例は、いずれもプライバシーを最優先に考慮し、個人が特定されないように配慮したうえで掲載しています。具体的には、当事者の同意を得たうえで、一部の属性や背景を変更したり、複数のケースを参考にして再構成したりすることで、個人や企業を特定できないように工夫しています。読者の皆さまが安心して事例に触れられるよう、守秘義務とプライバシー保護を徹底して取り組んでおりますので、安心してお読みいただければ幸いです。
ボランティア活動や講演会の場
自治体やNPOが主催するボランティア活動や講演会も、地域コミュニティとのつながりをつくる良い機会になります。とくに、
-
メンタルヘルス関連の講演会
- 「うつ」「DV」「子どもの非行」など、広く募集される講演やセミナーの中に、人格障害の話題を扱うコーナーがあるかもしれません。そこに参加すると、同じ問題意識を持つ人と出会えることも。
-
カウンセリング講座・コミュニケーション講座
- 市区町村や社会福祉協議会などが無料や低料金で開く場合があります。そこで“バリデーション”や“アサーティブコミュニケーション”など実践的なスキルを学べる可能性も。
あなたへのメッセージ
「こんなことでボランティアなんてできるわけがない」「そんな余裕ない…」と思われるかもしれません。しかし、外に足を踏み出すことで、自分の苦しさを俯瞰できたり、「もっと悩んでる人もいるんだ」と知って励まされたりする例は多いです。無理のない範囲で、負担にならない程度に関わってみるだけでも、自分の世界が広がるはずです。
2. 公的機関を頼る:相談・カウンセリング・専門家の導入
市区町村の福祉課・保健所
多くの自治体には、福祉課や保健所のメンタルヘルス相談があります。そこでは、以下のようなサポートを得られる可能性があります。
- 専門機関やクリニックの紹介
- 人格障害の特性を抱える家族が「病院には行きたくない」と拒否しても、まずは家族自身が相談し、診療科や病院を探すヒントを得られる。
- カウンセリングの場や家族会の情報
- 地域ごとにメンタルヘルス家族会やピアサポート団体が存在することが多く、保健所はそうした情報のハブ役になる。
保健師との連携で救われた妻【具体的な事例】
Cさん(妻)は、夫(自己愛性パーソナリティ障害かもしれない)のモラハラで精神的に追い詰められ、保健所のメンタルヘルス相談を訪れた。担当の保健師がじっくり話を聞き、「こういう支援団体がありますよ」「法律相談はここで受けられます」など具体的な選択肢を提示してくれた。Cさんはそれまで「家族の恥をさらすみたいで」と相談をためらっていたが、「思ったより親身に対応してくれるし、誰も私を責めなかった」と実感し、それをきっかけに夫と距離を置くための準備を進めることができたという。
※本記事で紹介している事例は、いずれもプライバシーを最優先に考慮し、個人が特定されないように配慮したうえで掲載しています。具体的には、当事者の同意を得たうえで、一部の属性や背景を変更したり、複数のケースを参考にして再構成したりすることで、個人や企業を特定できないように工夫しています。読者の皆さまが安心して事例に触れられるよう、守秘義務とプライバシー保護を徹底して取り組んでおりますので、安心してお読みいただければ幸いです。
児童相談所・家庭裁判所(子ども絡みの場合)
- 児童相談所
- 子どもが人格障害の特性を持ち、家族が日常的に振り回されている場合もあれば、親が人格障害を持ち子どもが被害を受けているケースもある。いずれも相談先として児童相談所が利用できる。
- 「そこまで深刻じゃないかも…」と思っても、少しでも不安があれば問い合わせてみるといい。
- 家庭裁判所
- 親が人格障害の特性を持ち、子どもに対して虐待的な言動をしている場合、離婚や親権問題を扱う中で家庭裁判所が関わることも。
- 兄弟姉妹間でも相続問題や後見人の選任などで家裁が関わるシーンがある。
専門的な解説
人格障害の特性を有する家族が絡む子育てや相続問題は、法律面や子どもの安全確保が最優先となる場合があります。日本の福祉制度・司法制度には細かな手続きが多いですが、一度動き出すと意外にもスムーズにサポートを受けられる可能性があります。専門家(弁護士やソーシャルワーカー)に仲介してもらうことで、家族だけでは解決困難な問題をクリアできるかもしれません。
3. 家族会・支援グループ:同じ悩みを共有する仲間を見つける
なぜ家族会が役立つのか
家族会(たとえば境界性パーソナリティ障害の家族会、自己愛性パーソナリティ障害に悩む家族会など)は、同じ問題を抱える人々が集まって情報交換や気持ちの共有を行う場です。そこで得られるメリットは、
- 「うちだけじゃない」と知る安心感
- 人格障害の特性を持つ家族がいることで苦しんでいるのは自分だけではない、とわかるだけで精神的に救われる。
- 実践的な対処法の共有
- 先に同じ道を経験した人たちから「こんな専門家に相談したらよかった」「こういうコミュニケーション技術が役立った」などの具体例を聞ける。
- 愚痴や本音を話せる場所
- 周囲に言いにくい家族の問題も、家族会なら誰も否定せず理解してくれる。攻撃される心配がないので言葉を吐き出せる。
家族会で救われた母親【具体的なエピソード】
Dさん(母親)は、息子(反社会性パーソナリティ障害の可能性)に振り回され、金銭トラブルや暴力に悩んでいた。夫は「息子なんだから仕方ない」と取り合わず、Dさんは「こんなのもう耐えられない」と孤立感を深めていた。そんなとき、ネットで見つけた家族会に試しに参加。初回は緊張したが、そこには同じように息子の非行に苦しむ人、DVや金銭搾取に苦しむ人などがいて、それぞれの体験を話し合っていた。
Dさんは初めて「あなたもすごく大変だったのね」「わかる、その辛さ」と言ってもらい、涙が止まらなかったという。その会で法律相談の活用法を教わり、弁護士経由で息子に借金を返済させるプロセスを進めるなど、具体的行動に移せたとのこと。
※本記事で紹介している事例は、いずれもプライバシーを最優先に考慮し、個人が特定されないように配慮したうえで掲載しています。具体的には、当事者の同意を得たうえで、一部の属性や背景を変更したり、複数のケースを参考にして再構成したりすることで、個人や企業を特定できないように工夫しています。読者の皆さまが安心して事例に触れられるよう、守秘義務とプライバシー保護を徹底して取り組んでおりますので、安心してお読みいただければ幸いです。
4. オンラインリソースとSNS:匿名だから話せること
SNS・掲示板の活用
家族問題は口頭での相談が難しく、「恥ずかしい」「地域の人に知られたくない」と思うことも多いでしょう。しかし、SNSや匿名掲示板であれば、自分の身元を明かさずに同じ悩みを抱える人々と意見交換できます。
- Twitter(X)やInstagram: ハッシュタグ(例:「#境界性パーソナリティ障害家族」「#自己愛性家族」など)を追うと、当事者や家族のリアルな声が見つかる可能性がある。
- 5ちゃんねる、Yahoo!知恵袋: 誹謗中傷も多いが、中には実体験ベースのアドバイスが得られるトピックも。見極めは必要だが、感情吐露の場として活用できる。
- 専門サイトやNPOの掲示板: 人格障害やメンタルヘルスに特化したNPOや団体が運営する掲示板・チャットには、経験豊富なスタッフや家族当事者が集まっている。
注意点
- 誹謗中傷やデマ情報に巻き込まれるリスクがあるので、鵜呑みにせず参考程度に。
- 個人情報の扱い: 匿名性があるとはいえ、家族が特定されかねない詳細を書きすぎないように注意。
5. 「地域・コミュニティリソースを使う」という選択への抵抗感を乗り越える
「家族の問題を他人に知られるなんて……」という気持ちや、「周りに迷惑かけたくない」という遠慮が根強いと、地域やコミュニティとのつながりを作り出すことが難しくなる場合があります。しかし、人格障害の特性による家庭内問題は、長期化・深刻化すると、むしろ多くの迷惑や悲劇を生んでしまう恐れがあるのです。
- 自分が倒れる前にアクションを
- トラブルが軽度のうちに外部リソースを探しておくと、深刻化してから動くよりも楽。
- 相手(人格障害の可能性がある家族)を説得しようとしすぎない
- 相手に「地域の支援を使おうよ」と言っても拒否される場合が多い。まずは自分が相談して準備を整えておく。
- 周囲が知らないからこそ新たな支援が得られる
- 意外と周囲の人々は、あなたの苦しみを知れば「そんな大変なことになってたなら、もっと早く言ってよ」とサポートしてくれることもある。
6. 実際の改善事例:地域資源をうまく活用した兄弟
※本記事で紹介している事例は、いずれもプライバシーを最優先に考慮し、個人が特定されないように配慮したうえで掲載しています。具体的には、当事者の同意を得たうえで、一部の属性や背景を変更したり、複数のケースを参考にして再構成したりすることで、個人や企業を特定できないように工夫しています。読者の皆さまが安心して事例に触れられるよう、守秘義務とプライバシー保護を徹底して取り組んでおりますので、安心してお読みいただければ幸いです。
-
兄弟同士で“家族会”に参加し、問題を共有
- 姉が自己愛性、弟が依存性という異なるタイプの人格障害を抱え、家族全体が疲弊していたケース。親は「どうすればいいかわからない」と混乱。
- 地域の家族会に両親が通い始め、そこで得た情報をきっかけに「姉はカウンセリング、弟は障害福祉サービスの一部を活用」とそれぞれ専門的サポートを受けられた。
- 初期は反発もあったが、姉が自分の言動を省みるきっかけとなり、弟も外部の就労支援プログラムを利用するなど、少しずつ家族の機能が回復した。
-
地域包括支援センターを活用して親子の問題を整理
- 高齢の親が境界性パーソナリティ障害的な行動を示し、成人した子どもを過剰に束縛。子どもは同居して介護していたが、限界を感じ「地域包括支援センター」に相談。
- センターのスタッフが家庭訪問し、親に対して在宅介護サービスの利用やデイケアの提案などを行い、子どもの負担軽減のために手続きをサポート。
- 親は最初「私は元気だからいらない!」と拒否したが、スタッフの継続的な説得や子どもの疲弊ぶりを理解し、最終的にデイサービスに通うようになったことで、子どもは日中自由時間を持てるように。
7. 周囲との連携はあなた自身を救うカギ
「家族の問題だから、家の中だけで解決しなくては」と考えると、人格障害の特性を持つ家族とのトラブルは泥沼化しがちです。しかし、地域やコミュニティには思っている以上に多様なリソースが存在します。以下のポイントを改めて確認してください。
-
自治体やNPO、ボランティア団体に目を向ける
- メンタルヘルスやDV、家族問題を扱う相談窓口が多数ある。家族会やサポートグループなど、仲間と出会える場所があるかもしれない。
-
公的機関の専門的サポート
- 保健所、児童相談所、家庭裁判所など。法律問題や介護問題が絡む場合は、法テラスや専門家(弁護士・司法書士など)を頼る。
- 必要に応じてカウンセリングや家族療法も選択肢になる。
-
オンラインコミュニティやSNSの力
- 匿名で悩みを共有できる掲示板やSNSは、家族や周囲には言えない本音を吐き出せる場として有効。
- ただし情報の真偽には注意しつつ、参考にできる部分だけ取り入れる。
-
行動すること自体が突破口
- とりあえず相談だけでもしてみる、セミナーに出てみる、コミュニティの集まりをのぞいてみる…。一歩動くことで、新しい発見や人脈が得られる。
最後に、家族内の問題は相手を変えるのが難しいぶん、自分自身を守るためにも周囲のリソースを活用することが鍵となります。「こんなことで迷惑をかけるのは…」と尻込みしてしまうかもしれませんが、苦しんでいるまま行き詰まるよりは、だめもとで声を上げてみる価値は大いにあります。支援団体や地域コミュニティは、あなたの状況を非難するのではなく、「手助けが必要なんだね」と受け止めてくれる可能性が高いのです。
家族に人格障害の特性をもつ人がいることで消耗しきっているあなたへ——一人で抱え込まず、ぜひ地域やコミュニティとの“架け橋”を作ってみてください。ほんの少し相談するだけで、「それならこんなサービスがあるよ」「こんな人もいるよ」と思わぬ情報が舞い込んでくるかもしれません。あきらめずに行動すれば、家族の関係性に小さな変化が生まれ、あなた自身が生活の質を取り戻せる日がきっとやってくるはずです。どうか今の苦しい気持ちを一人で抱え込まないでいてくださいね。あなたは決して孤独ではありませんし、周囲との連携はあなたを救う大きなカギとなります。応援しています。

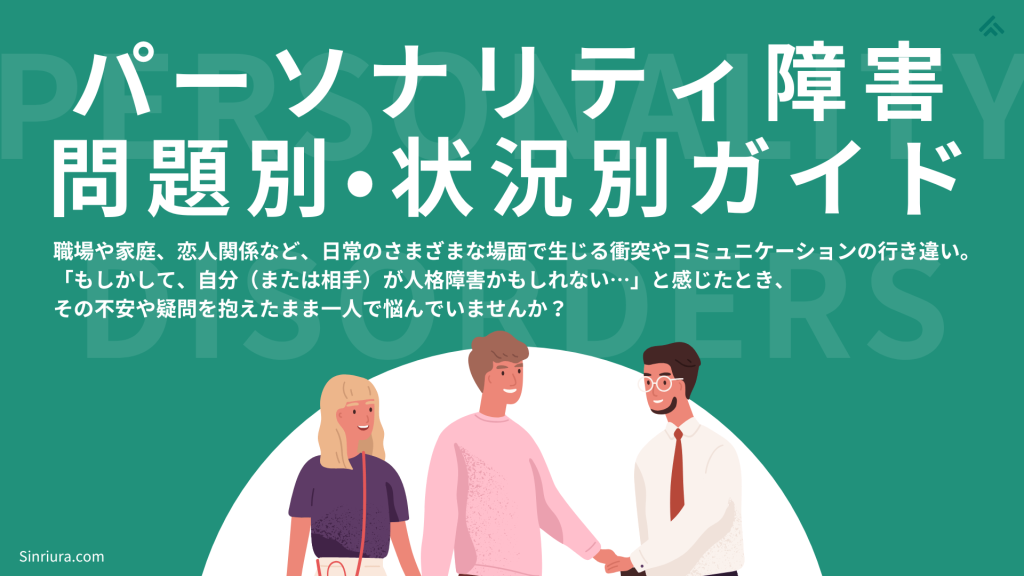
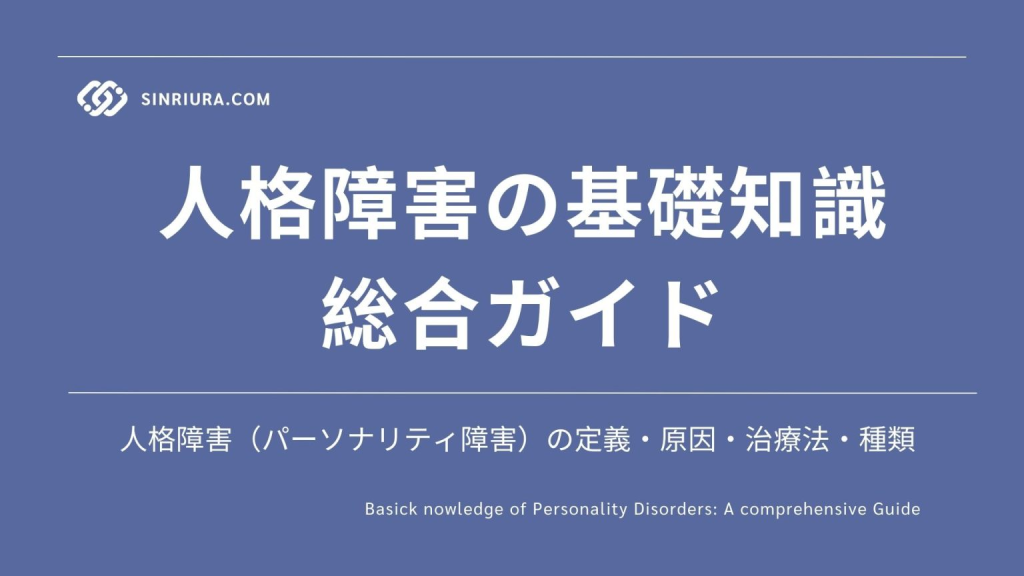
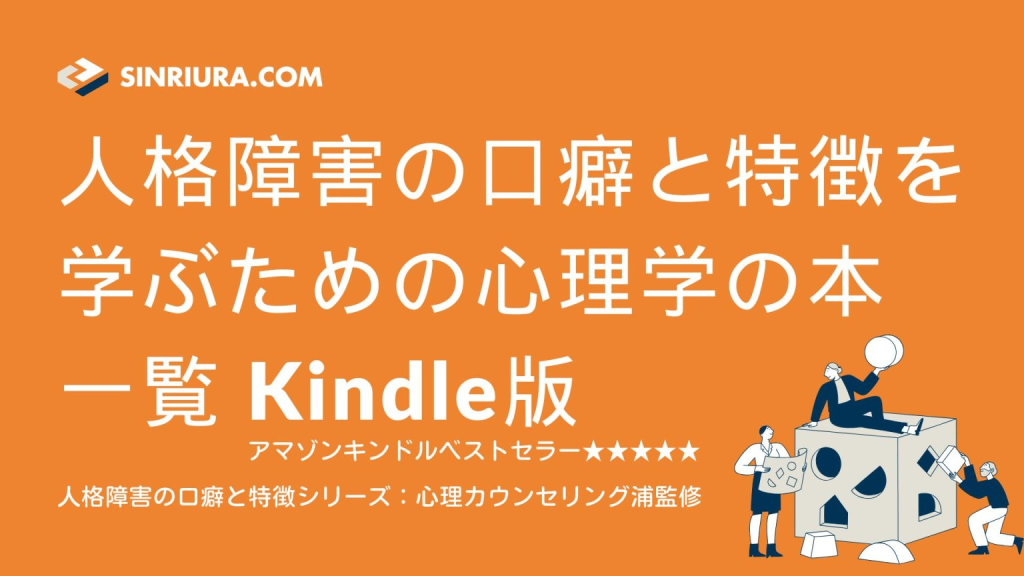
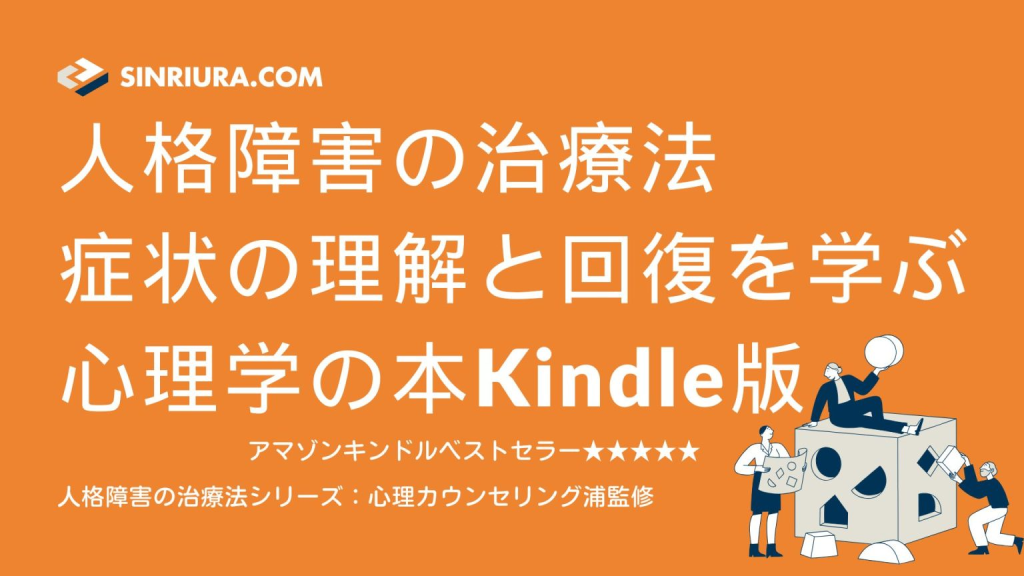

家庭内でのパーソナリティ障害に関する参考文献・参考資料URL一覧
「家庭での人格障害への対応策」に関連する参考資料および参考文献のURL一覧をまとめました。これらのリソースを活用して、さらに深い理解と具体的な支援策を得ることができます。
厚生労働省: パーソナリティ障害に関する情報
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196752.html
日本精神神経学会: パーソナリティ障害の概要
URL: https://www.jspn.or.jp/modules/public/index.php?content_id=30
国立精神・神経医療研究センター: パーソナリティ障害の原因とメカニズム
URL: https://www.ncnp.go.jp/psychiatry/character_disorder
日本精神保健福祉士会: 家庭内でのパーソナリティ障害の影響と対策
URL: https://www.jsw-w.jp/public_info/family_disorder
NPO法人こころの相談室: 家庭内でのパーソナリティ障害対策
URL: https://www.kokoro-shindan.jp/family_support
NPO法人家庭の相談: 境界性パーソナリティ障害の支援
URL: https://www.kateino-soudan.jp/bpd_support
法テラス: 無料法律相談サービス
URL: https://www.houterasu.or.jp/
地域包括支援センター: 家庭内トラブル支援サービス
URL: https://www.mhlw.go.jp/kousei/chiiki_houkatsu.html
日本精神保健福祉士会: 境界線設定の方法と重要性
URL: https://www.jsw-w.jp/public_info/boundary_setting
臨床心理士協会: 効果的なコミュニケーション技術
URL: https://www.clinicalpsychologist.or.jp/communication_techniques
日本心身医学会: 自己ケアとストレス管理
URL: https://www.jkmu.jp/self_care
日本法テラス: 法的支援と相談サービス
URL: https://www.houterasu.or.jp/
児童相談所: 子どもの安全と福祉の確保
URL: https://www.mhlw.go.jp/kodomo/child_consultation.html
日本臨床心理士会: 臨床心理士の役割
URL: https://www.jsccp.or.jp/role_of_clinical_psychologists
NPO法人サポートネットワーク: 家族支援グループ
URL: https://www.support-network.jp/family_groups
DSM-5日本語版解説書
出版社: 東京医療出版
URL: https://www.tokyomedicalpub.jp/dsm5
NPO法人家庭の相談: 境界性パーソナリティ障害の支援
URL: https://www.kateino-soudan.jp/bpd_support
アサーティブ・コミュニケーションの基本と実践
URL: https://www.assertive-communication.jp/basics
目標設定と期待管理の心理学
URL: https://www.psychology-goals.jp/expectation_management
日本法テラス: 法的手続きとプライバシー保護
URL: https://www.law-privacy.jp/legal_protection
NPO法人こころの相談室
URL: https://www.kokoro-shindan.jp/
NPO法人家庭の相談
URL: https://www.kateino-soudan.jp/
NPO法人サポートネットワーク
URL: https://www.support-network.jp/
日本精神科医会: 精神科医の役割と支援内容
URL: https://www.jspn.or.jp/modules/public/index.php?content_id=31
心理カウンセリングの倫理とプライバシー保護
URL: https://www.psych-counseling-ethics.jp/privacy
回避性パーソナリティ障害の理解と克服
URL: https://www.avpd-understanding.jp/
依存性パーソナリティ障害の症状と治療法
URL: https://www.dpd-symptoms.jp/treatment
反社会性パーソナリティ障害の特徴と支援
URL: https://www.aspd-characteristics.jp/support
境界性パーソナリティ障害の理解と対策
URL: https://www.bpd-understanding.jp/
自己愛性パーソナリティ障害の診断と治療
URL: https://www.npd-diagnosis.jp/treatment
DSM-5日本語版解説書
出版社: 東京医療出版
URL: https://www.tokyomedicalpub.jp/dsm5
NPO法人家庭の相談: 境界性パーソナリティ障害の支援
URL: https://www.kateino-soudan.jp/bpd_support
メンタルヘルス支援のための総合ガイド
URL: https://www.mentalhealth-guide.jp/
日本心身医学会: 自己ケアとストレス管理
URL: https://www.jkmu.jp/self_care
家庭内トラブル対策のガイドライン
URL: https://www.family_troubleshoot.jp/guidelines
自己防衛と関係改善の心理学的アプローチ
URL: https://www.psychology-balance.jp/self_defense_relational_improvement
日本臨床心理士会: 臨床心理士の役割
URL: https://www.jsccp.or.jp/role_of_clinical_psychologists
日本精神保健福祉士会: 境界線設定の方法と重要性
URL: https://www.jsw-w.jp/public_info/boundary_setting
地域包括支援センター: 総合的な福祉サービスの提供
URL: https://www.mhlw.go.jp/kousei/chiiki_houkatsu.html
日本精神神経学会: パーソナリティ障害の概要
URL: https://www.jspn.or.jp/modules/public/index.php?content_id=30
これらの参考文献や資料を活用することで、家庭内での人格障害への対応策をより深く理解し、具体的な支援を得るための手助けとなるでしょう。専門家や公的機関のサポートを積極的に利用し、健全な家庭関係の構築に役立ててください。

