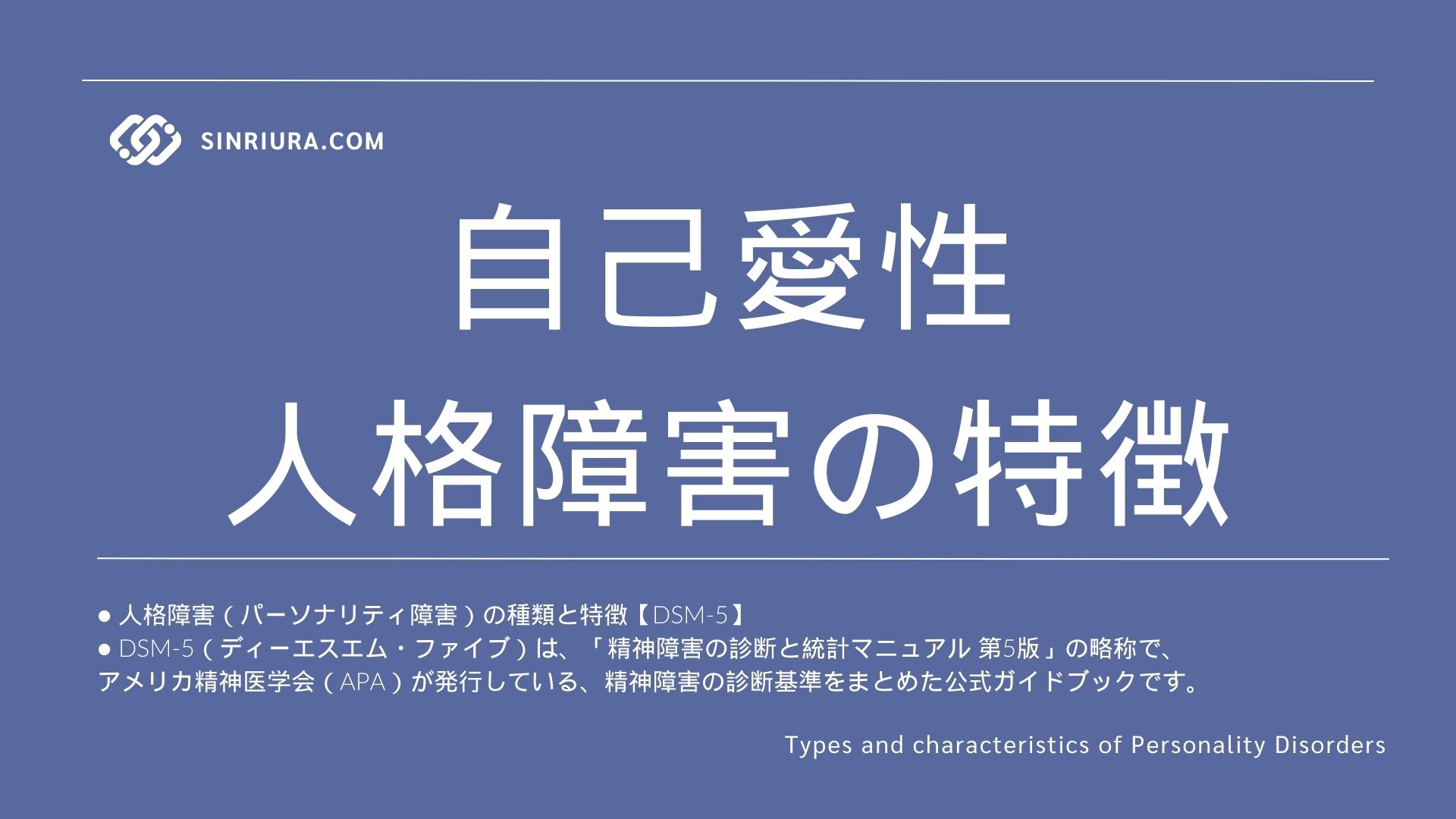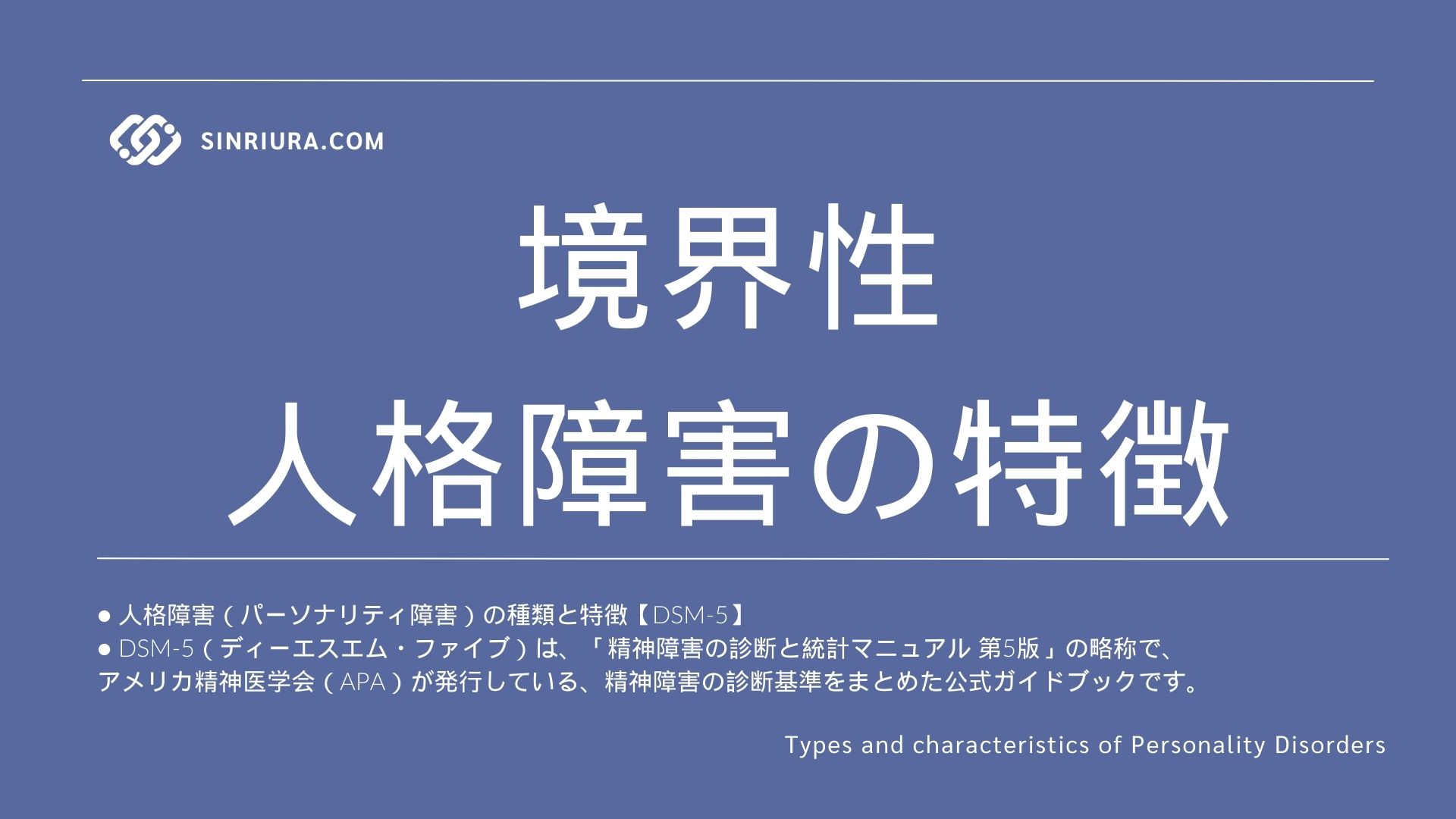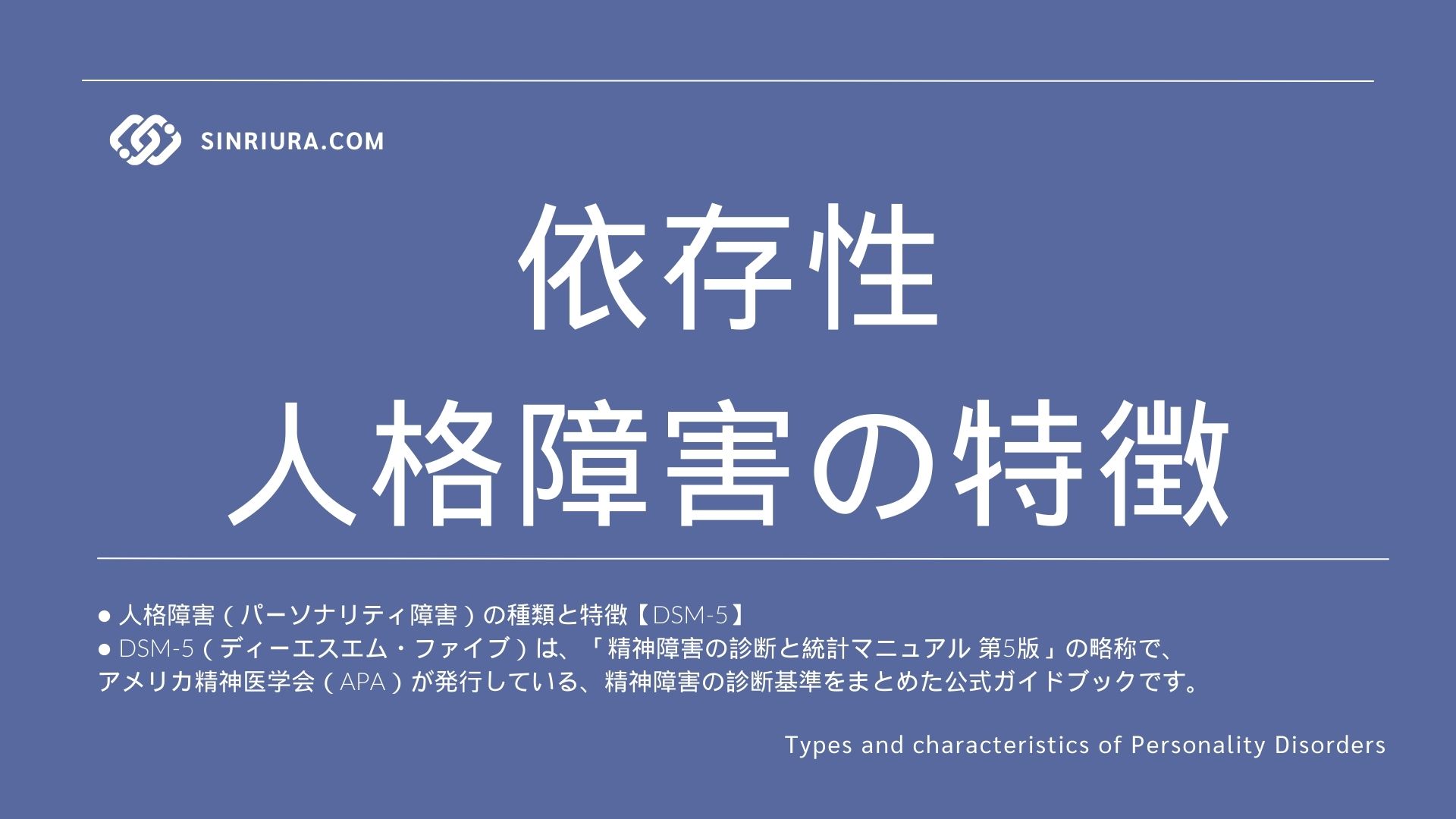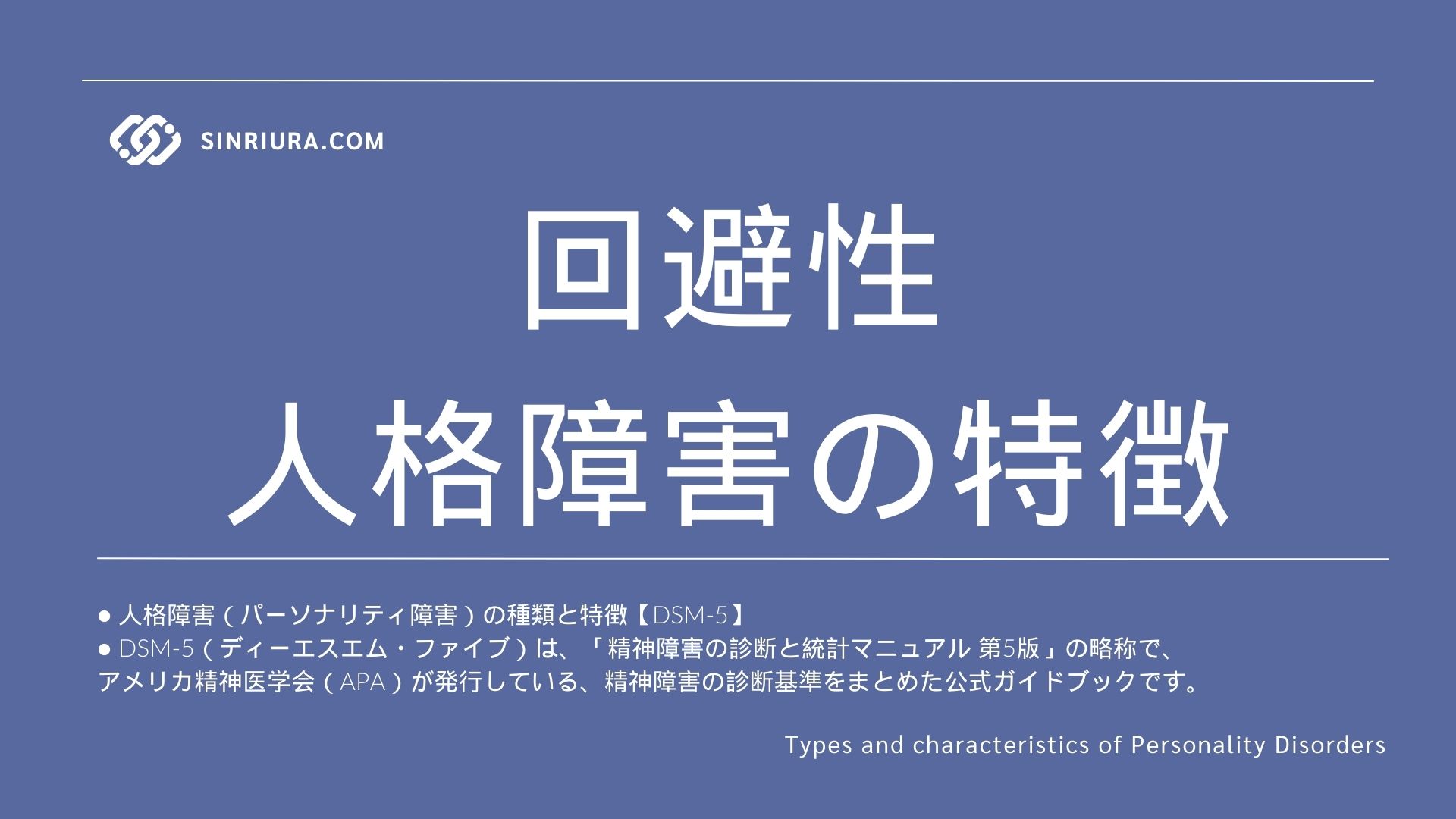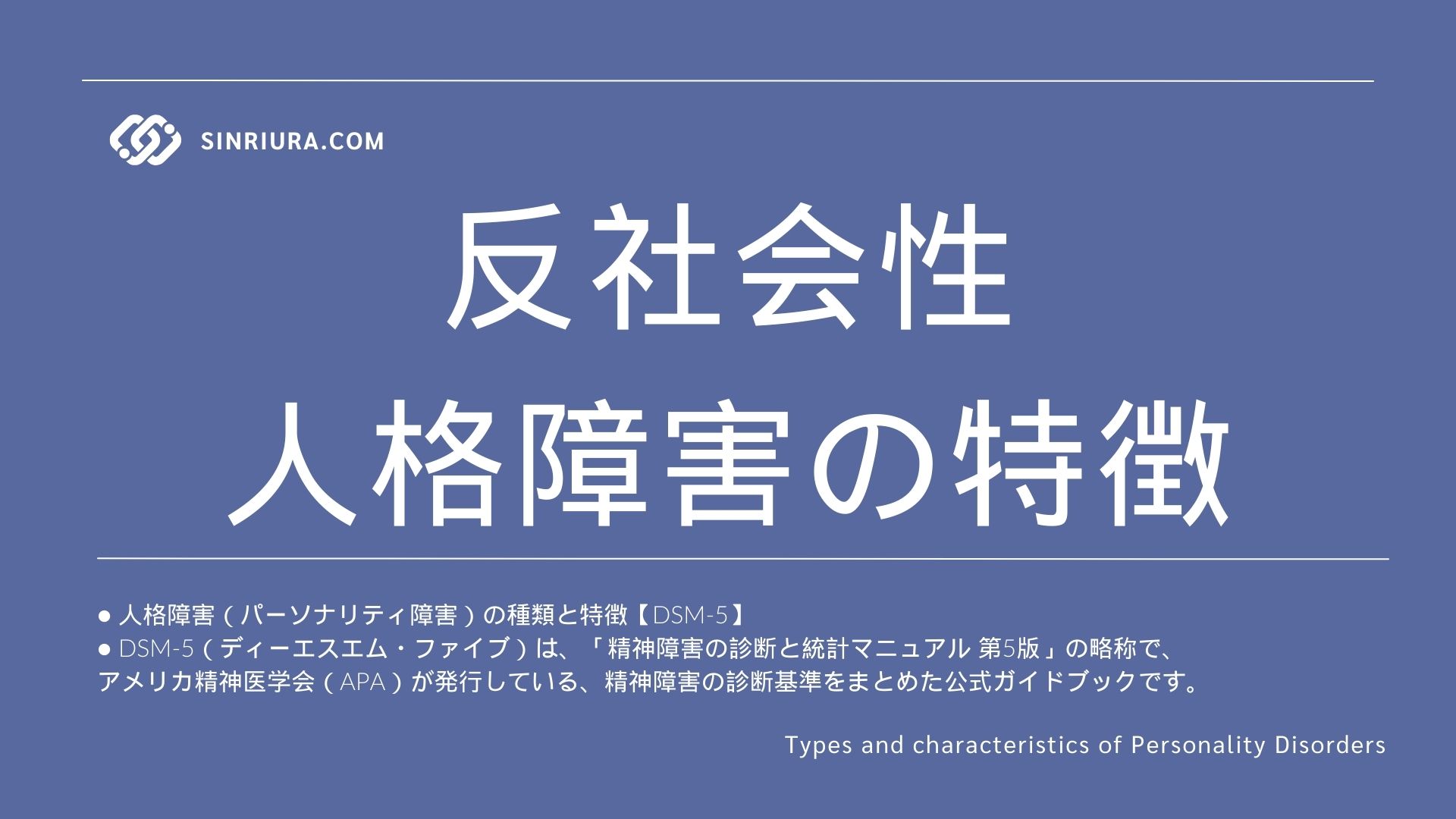もう悩まない!人格障害の部下や同僚への対処法
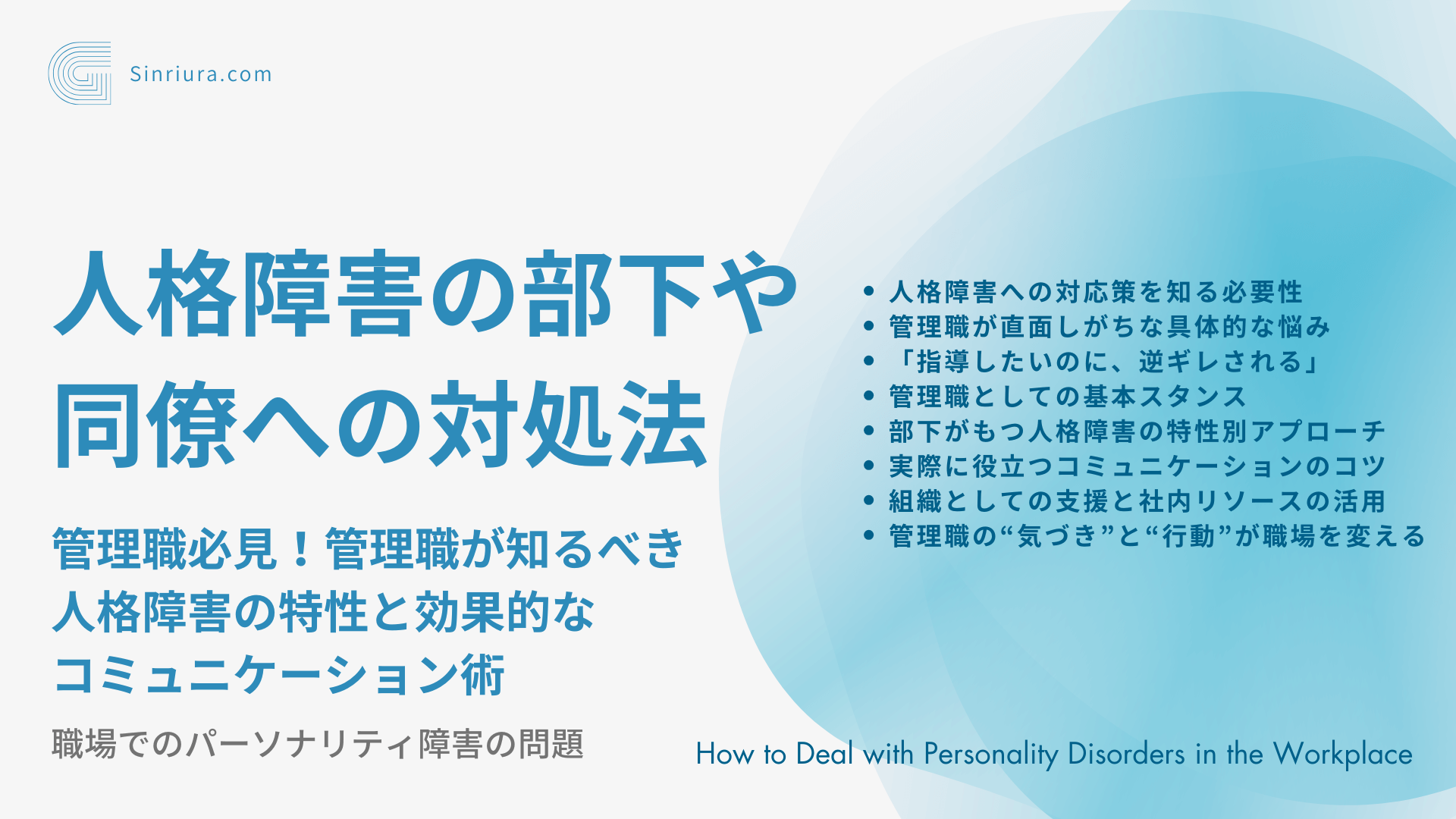
管理職必見!管理職が知るべき人格障害の特性と効果的なコミュニケーション術
「部下を育てたいのに、ちょっとした言葉がきっかけで激しく反発される」「何度手助けしても、一向に自信を持てず仕事を任せられない」——管理職としてこうした悩みを抱え込んでいませんか?
実は、部下や同僚に人格障害(パーソナリティ障害)の特性があると、通常の指導法やコミュニケーションではうまくいかない場合が多々あります。相手の不安定な言動に振り回され続けるうちに、今度は管理職であるあなた自身が限界を感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、「相手が厄介だから仕方ない」「私が弱いせいでうまく指導できない」と思い詰めるばかりでは、状況はなかなか改善しません。そこで大切なのが、相手の特性を理解したうえで、自分の接し方を少し変えてみるという姿勢。さらに、業務を円滑に進めるためには、必要に応じて周囲や社内リソースと連携しながら、組織全体で問題に取り組むことが求められます。
本記事では、管理職だからこそ知っておきたい「人格障害を持つ部下や同僚への具体的な対応策」について、深掘りして詳しく解説しました。日々の指導やマネジメントが思うようにいかず、ストレスを感じている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。小さな一歩を踏み出すだけで、あなたとチームの両方を救う大きな変化が訪れるはずです。
愛知県名古屋市の心理カウンセラー 浦光一
目次
- なぜ管理職が人格障害への対応策を知る必要があるのか
- 管理職が直面しがちな具体的な悩み
2-1. 「指導したいのに、逆ギレされる」
2-2. 「仕事の進め方を教えても、自信がないとすぐに投げ出される」
2-3. 「周囲を巻き込むトラブルが絶えず、他のメンバーにも悪影響が…」 - 管理職としての基本スタンス:境界を保ち、客観性を意識する
- 部下がもつ人格障害の特性別アプローチ
4-1. 自己愛性パーソナリティ障害(Narcissistic Personality Disorder)
4-2. 境界性パーソナリティ障害(Borderline Personality Disorder)
4-3. 依存性パーソナリティ障害(Dependent Personality Disorder)
4-4. 回避性パーソナリティ障害(Avoidant Personality Disorder)
4-5. 反社会性パーソナリティ障害(Antisocial Personality Disorder) - 実際に役立つコミュニケーション・マネジメントのコツ
5-1. 状況把握のための記録習慣
5-2. アサーティブコミュニケーション
5-3. チーム全体への配慮:情報共有と“心理的安全性”の醸成 - 組織としての支援と社内リソースの活用
- まとめ:管理職の“気づき”と“行動”が職場を変える
1. なぜ管理職が人格障害への対応策を知る必要があるのか
管理職は、チームの成果を最大化しながら、メンバー一人ひとりの成長を促すという重要な役割を担っています。しかし、部下の中に人格障害の特性を持つ方がいる場合、通常の指導方法ではうまくいかないケースが少なくありません。たとえば「少し強めに指導しただけで極端に落ち込む」「ちょっとした評価の差にも大きな反応を示す」など、一般的なフィードバックでは制御不能な場面に直面することがあります。
その結果、「どう対応すればいいのかわからない」「どこまで厳しく言うべきか、どこまで優しくすべきか」と管理職自身が混乱し、最悪の場合はメンタル不調に陥ってしまうことさえ珍しくありません。さらに、人格障害の特性を持つ部下とのトラブルは、他のメンバーにも影響を及ぼすため、チーム全体の士気や業務効率を下げる要因となり得ます。
一方で、人格障害は「治らない性格の問題」ではありません。適切な理解と接し方があれば、症状や行動パターンを緩和できる可能性があるのです。そのためには、管理職がまず「相手の行動の背景を知る」「関係をどう築くかを工夫する」という姿勢を持ち、場合によっては専門家や組織内リソースを活用することが不可欠です。
2. 管理職が直面しがちな具体的な悩み【事例】
ここでは、多くの管理職が経験するであろう具体的な人間関係の悩みを取り上げ、具体的な事例を一緒に見ていきながら問題を掘り下げていきます。似たようなシチュエーションを思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。
※本記事で紹介している事例は、いずれもプライバシーを最優先に考慮し、個人が特定されないように配慮したうえで掲載しています。具体的には、当事者の同意を得たうえで、一部の属性や背景を変更したり、複数のケースを参考にして再構成したりすることで、個人や企業を特定できないように工夫しています。読者の皆さまが安心して事例に触れられるよう、守秘義務とプライバシー保護を徹底して取り組んでおりますので、安心してお読みいただければ幸いです。
2-1. 「指導したいのに、逆ギレされる」
事例:
- 部下がプレゼン資料の内容を幾度もミスするため、丁寧に指摘しただけなのに、「そんなふうに言われるなら、もうやる気ないです!」と怒鳴って席を立ってしまう。
- 「どうしてここまで激昂するのか…自分の言い方が問題だったのだろうか?」と落ち込みつつも、誠実な指導をしようとしているのに報われない感覚が残る。
管理職の気持ち:
- 「ただ業務上のミスを改善してほしいだけなのに、相手が感情的になりすぎて正論が届かない…」
- 「自分も悪いのかもしれないが、ここまで責められると胃が痛くなる」
2-2. 「仕事の進め方を教えても、自信がないとすぐに投げ出される」
事例:
- 新人の部下が、タスクの説明をしても「私なんてできません…」と被害的になり、結局他のメンバーに仕事を振らなければならない状況が続く。
- 何度も「大丈夫だよ、少しずつ覚えればいいよ」と声をかけても、「私には無理です」の一点張りで業務が回らない。
管理職の気持ち:
- 「サポートはしているつもりでも、本人があまりに悲観的だと手の打ちようがない」
- 「ほかのメンバーにも負担が偏っていて、チーム全体の士気が下がりそうで怖い」
2-3. 「周囲を巻き込むトラブルが絶えず、他のメンバーにも悪影響が…」
事例:
- 自己愛性パーソナリティ障害の傾向を持つ部下が、プロジェクトの成果を常に自分のものにしようと画策。周りの意見を無視し、同僚との衝突が絶えない。
- 「あの人と組むと必ず仕事がこじれる」と社員全体の噂になっており、配置転換を望む声が多くなる。
管理職の気持ち:
- 「放っておくと組織全体が不満まみれになる。けれども、この人を排除するのが正解かどうか…」
- 「スキルや能力はあるのに、人格面で問題が多くて評価に苦しむ」
3. 管理職としての基本スタンス:境界を保ち、客観性を意識する
前述のような悩みを抱える管理職の方々が、まず押さえておきたいのは「境界(バウンダリー)を意識する」ことと「客観性を持つ」ことです。人格障害の特性を持つ人は、感情のコントロールが苦手だったり、他人との距離感が極端だったり するため、上司を含む周囲の人々が振り回されがち。その結果、管理職が疲弊し、適切な指導や判断ができなくなることが少なくありません。
-
境界を保つ:
- 部下の課題と自分の課題を混同しない。「相手が勝手に怒る部分」は部下の問題、「その状況にどう対処するか」は管理職としての自分の課題。
- 過度な干渉や過剰な擁護は避けつつ、必要な支援を見極める。
-
客観性を意識する:
- 「この人はおかしい」とレッテル貼りするのではなく、「こういう特性が考えられる」と仮説を立てて対応策を検討する。
- 感情的な応酬に巻き込まれず、できるだけ事実ベースでやり取りを進める。
こうした基本スタンスを保つことが、対処策を考えるうえでの土台となります。
4. 部下がもつ人格障害の特性別アプローチ
管理職の悩みの多くは、「言ってもわからない」「なぜこうなるのか理解できない」というところにあります。そこで、ここでは代表的な人格障害(パーソナリティ障害)の特性に合わせたアプローチ法を紹介します。もちろん専門家の診断が必要ですが、「もしかして…」という気づきがあるだけでも対応策は変わります。
4-1. 自己愛性パーソナリティ障害(Narcissistic Personality Disorder)
-
特徴:
- 承認欲求が非常に強い
- 自分が常に中心でありたい
- 批判に極端に弱い
-
管理職の対応策:
- 承認欲求を程よく満たす: 多少の称賛や評価を与えることで、大きな衝突を防ぎやすい。ただし、過剰に持ち上げすぎると相手の傲慢さを助長する可能性があるのでバランスが大事。
- 事実ベースでフィードバック: 「あなたのここは良かった。でも、これも他の人の協力があってこそ」と具体的な成果や周囲の貢献を示す形で冷静に伝える。
- 批判は婉曲的に: 厳しい指摘をする際は、行動や事実のみを取り上げ、人格を否定するような表現は避ける。そのうえで建設的な改善策を明確に示す。
👉 「自己愛性パーソナリティ障害の特徴について詳しく解説」を読む
4-2. 境界性パーソナリティ障害(Borderline Personality Disorder)
-
特徴:
- 感情の起伏が激しい
- 見捨てられ不安が強く、依存と攻撃を繰り返す
- 対人関係が極端(理想化と失望の繰り返し)
-
管理職の対応策:
- バリデーション(validation): 相手の感情そのものは否定せず、「そんなにつらいんだね」と受け止める姿勢を示す。ただし、相手の要求や行動をすべて受け入れる必要はない。
- 安定した対応: 管理職が日によって態度を変えすぎると、相手の見捨てられ不安をあおる可能性がある。なるべく一貫した態度で接する。
- 専門家につなぐ: 感情コントロールが極端に苦手で業務に支障をきたす場合、産業医や社内カウンセラーを通じて治療やカウンセリングを勧める。
👉 「境界性パーソナリティ障害の特徴について詳しく解説」を読む
4-3. 依存性パーソナリティ障害(Dependent Personality Disorder)
-
特徴:
- 自分で決断できず、他者に頼りがち
- 見放されることへの恐怖から、指示を求め続ける
- 責任を持とうとせず、失敗を恐れるあまり何もできなくなる
-
管理職の対応策:
- 段階的に仕事を任せる: いきなり大きなタスクを与えるとパニックに陥ることが多い。まずは小さな成功体験を積ませ、自信を育てる。
- 共感しつつも、責任は本人に返す: 「不安なのはわかるけど、最終決定はあなたがするんだよ」と明確に示す。
- 周囲のサポート体制: 他のメンバーにも依存しすぎる可能性があるため、あらかじめ「ここまではサポートしてもOK」「これは自分でやるべき」とルールを決めておく。
👉 「依存性パーソナリティ障害の特徴について詳しく解説」を読む
4-4. 回避性パーソナリティ障害(Avoidant Personality Disorder)
-
特徴:
- 人に批判される恐怖が強く、自分から関わりを避ける
- 自己評価が低い
- チャレンジを放棄しがち
-
管理職の対応策:
- 安全な環境を提供: 「失敗してもいいから挑戦してみよう」と伝え、フィードバックもまず前向きな部分を強調する。
- 無理な社交は強要しない: 飲み会やイベントなど集団行動を避ける人が多いが、それを無理に引き込もうとすると逆効果になる可能性がある。
- 徐々に目標を段階アップ: 急に難易度の高い業務を任せるより、ステップを少しずつ上げ、できた部分を認めることで自尊感情を高める。
👉 「回避性パーソナリティ障害の特徴について詳しく解説」を読む
4-5. 反社会性パーソナリティ障害(Antisocial Personality Disorder)
-
特徴:
- 他者の権利や社会規範を軽視
- 嘘や詐欺的行為に抵抗が少ない
- 共感が乏しく、衝動的
-
管理職の対応策:
- ルールと規範を明確に: 社内規定を徹底し、違反行為に対しては厳格に対処。甘い対応をするとエスカレートする可能性が高い。
- 法的問題を視野に入れる: 金銭的着服や他者へのハラスメントなどが疑われる場合、早めに人事やコンプライアンス部門と連携して対処する。
- 感情的アプローチは避ける: 「こんなことしてはいけないでしょ!」と感情的に叱責しても効果は薄い。行動の事実とルールの逸脱を指摘し、制裁を明確にするほうが有効。
👉 「反社会性パーソナリティ障害の特徴について詳しく解説」を読む
その他のパーソナリティ障害の種類と特徴
その他にも、職場で見られる人格障害(パーソナリティ障害)について、パーソナリティ障害の種類と特徴(DSM-5)について整理して詳しく解説しました。人格障害の種類と特徴について詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。
5. 実際に役立つコミュニケーション・マネジメントのコツ
人格障害の特性を持つ部下・同僚に対する対処法として、管理職が押さえておきたいポイントをいくつか挙げます。
5-1. 状況把握のための記録習慣
トラブルが起きたとき、管理職が感情に任せて動くと、後々「言った言わない」の水掛け論になることも。議事録やメールのやりとりをこまめに残し、いつ何が起きたかを客観的に把握する習慣が大切です。また、困った行動が続くなら、その日のメモや日報に書き留めておくと、専門家や上司に相談するときにも説得力が増します。
5-2. アサーティブコミュニケーション
先述のとおり、アサーティブな伝え方は、人格障害の特性を持つ人だけでなく、チーム全体のコミュニケーション向上に役立ちます。具体的には、
- 自分の意見をはっきり述べるが、相手の感情も認める
- 批判は行動や事実にフォーカスし、人格を否定しない
これだけでも衝突の原因をかなり緩和できます。もちろん、相手の特性が強いとすぐに理解されるわけではありませんが、少なくとも管理職として「感情に流されず、建設的に対話しようとしている」と周囲から評価されやすくなります。
5-3. チーム全体への配慮:情報共有と“心理的安全性”の醸成
「困った人」への対処は個別案件と考えがちですが、実際には周囲も巻き込まれていることが多々あります。そこで、
- チームミーティングの場などで「困ったときはこういう流れで相談しよう」「社内の相談窓口はここ」など、共通ルールを確認する。
- “心理的安全性”を高めるために、互いの意見を尊重できる場づくりを推進する。具体的には、お互いの意見を否定せずに受け取る訓練や、「ノーブレーム・アプローチ」(ミスを責めずに解決策を探る姿勢)を導入する。
6. 組織としての支援と社内リソースの活用
管理職が個人レベルで対応しきれない場合、早めに社内リソースを活用することも重要です。たとえば、
- 産業医やメンタルヘルス専門部署:部下のメンタルが深刻そうなら、直ちに専門家の評価を求める。管理職一人で抱え込む必要はない。
- ハラスメント相談窓口・コンプライアンス部門:パワハラや逆パワハラが疑われる場合は、組織の窓口へ報告し、公平な調査を依頼する。
- 人事異動や配置転換:人格障害の特性をもつ人と相性が悪いメンバーが過度に疲弊しないよう、上司同士で配置を調整することも検討する。
こうした手段をとることで、管理職自身が全責任を負わずに済むうえ、部下にとっても「必要な治療や支援」へつなぐきっかけが得られます。
7. 管理職の“気づき”と“行動”が職場を変える
人格障害を持つメンバーとの関わりは、ときに管理職の心身を追い込むほど困難が伴います。しかし、相手の特性を理解し、適切なコミュニケーションと組織リソースを活用することで、負担を軽減し、職場全体の健康を守ることが可能です。最後に要点をまとめます。
-
境界(バウンダリー)を明確に
- 自分が抱えるべき課題と、相手の問題を混同しない。
- 必要な支援は行いつつも、相手の感情に引きずられすぎない。
-
客観的な情報収集と記録
- できる限り事実ベースでコミュニケーションを進め、記録をこまめに残す。
- トラブルが生じた時点で、誰が何をいつ言ったかをメモする習慣をつける。
-
特性別アプローチを意識する
- 自己愛性、境界性など、タイプによって有効な声かけやサポート方法は異なる。
- 承認欲求の扱い方や感情調整のコツを把握しておくと、対立を減らせる。
-
チーム全体に配慮し、情報共有を怠らない
- 「彼(彼女)には要注意だ」と個別の問題にするのではなく、組織全体で支え合う仕組みづくりを。
- ミーティングや研修を活用して、“心理的安全性”の重要性を周知する。
-
社内外リソースを早めに活用する
- 産業医、カウンセラー、人事部などに相談し、専門的見地からのアドバイスを受ける。
- 法的問題が絡む場合は、ハラスメント窓口や弁護士への連絡も視野に。
管理職は会社の方針を現場に浸透させ、メンバーが能力を発揮できる環境を整える役割があります。しかし、それが一人ですべて解決できるとは限りません。だからこそ、まずは“気づき” ——問題を問題として認め、次に“行動” ——具体的な対策を講じることが肝心です。人格障害が絡む複雑なトラブルこそ、早期に情報を共有し、専門家や組織の力を借りることで大きく状況を変えることができます。
もし今、「もう限界かも…」「どう指導すればいいのか分からない」と感じる管理職の方がいらっしゃるなら、ぜひこれらのアプローチを試みつつ、周囲への相談を躊躇しないでください。あなたが少し動くだけで、職場全体が健全さを取り戻し、メンバーそれぞれが安心して働ける環境が近づくはずです。管理職としての知識とリーダーシップを生かし、より良いチームづくりを目指して一歩踏み出しましょう。
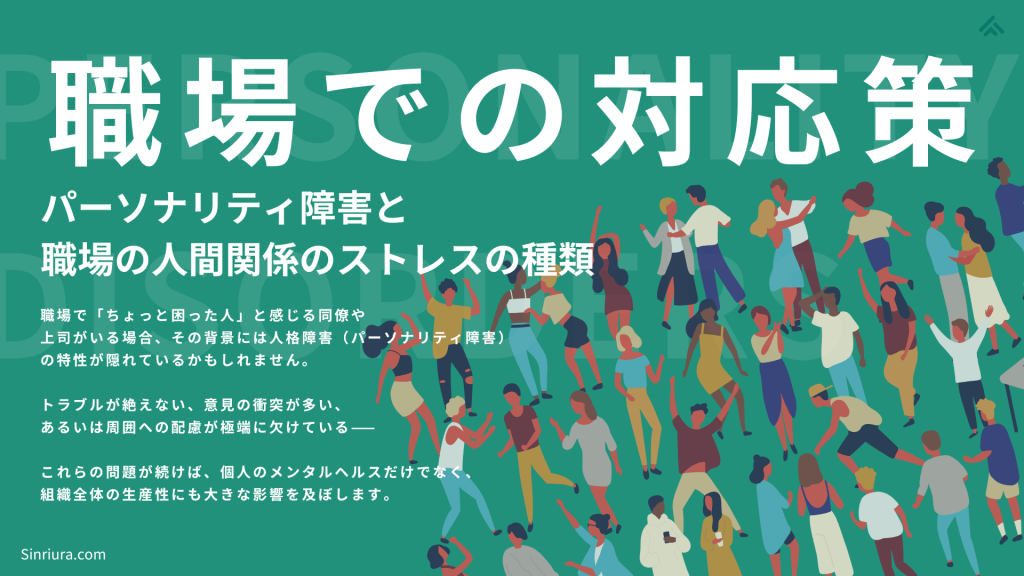
パーソナリティ障害に関する職場の人間関係のストレスと仕事の悩みを解決する方法
職場で「ちょっと困った人」と感じる同僚や上司がいる場合、その背景には人格障害(パーソナリティ障害)の特性が隠れているかもしれません。トラブルが絶えない、意見の衝突が多い、あるいは周囲への配慮が極端に欠けている——これらの問題が続けば、個人のメンタルヘルスだけでなく、組織全体の生産性にも大きな影響を及ぼします。
40年にわたる心理カウンセラーとしての現場経験から見えてきたのは、「相手を変えようとするのではなく、正しい知識を身につけて適切に対応する」ことの大切さ。この記事では、職場でよく見られるパーソナリティ障害のサインから、具体的な対応策、そして自分自身を守るストレスマネジメントまでをわかりやすく解説します。まずは、あなたの身近に起こる「困った状況」を改善するためのヒントを、一緒に探ってみましょう。
👉 「パーソナリティ障害に関する人間関係のストレスと仕事の悩みを解決する方法」を読む

パーソナリティ障害の問題別・状況別【対応ガイド】
職場や家庭、恋人関係など、日常のさまざまな場面で生じる衝突やコミュニケーションの行き違い。「もしかして、自分(または相手)が人格障害かもしれない…」と感じたとき、その不安や疑問を抱えたまま一人で悩んでいませんか?
人格障害(パーソナリティ障害)は、単なる「性格の問題」ではなく、本人や周囲の人々に深刻な影響を与える可能性があります。しかし、正しく理解し、適切な対策をとることで、関係性や日常生活は大きく改善できるのです。
この記事では、心理学初心者でもわかりやすいように、人格障害が引き起こす問題を「職場」「家庭」「パートナー関係」「子育て」「口癖」「思考パターン」など状況別に解説。さらに、セルフチェックや具体的なコミュニケーション術、専門家による治療やサポート情報まで網羅しています。自分や身近な人の悩みを少しでも軽くするために、まずは正しい知識を一緒に学んでみましょう。
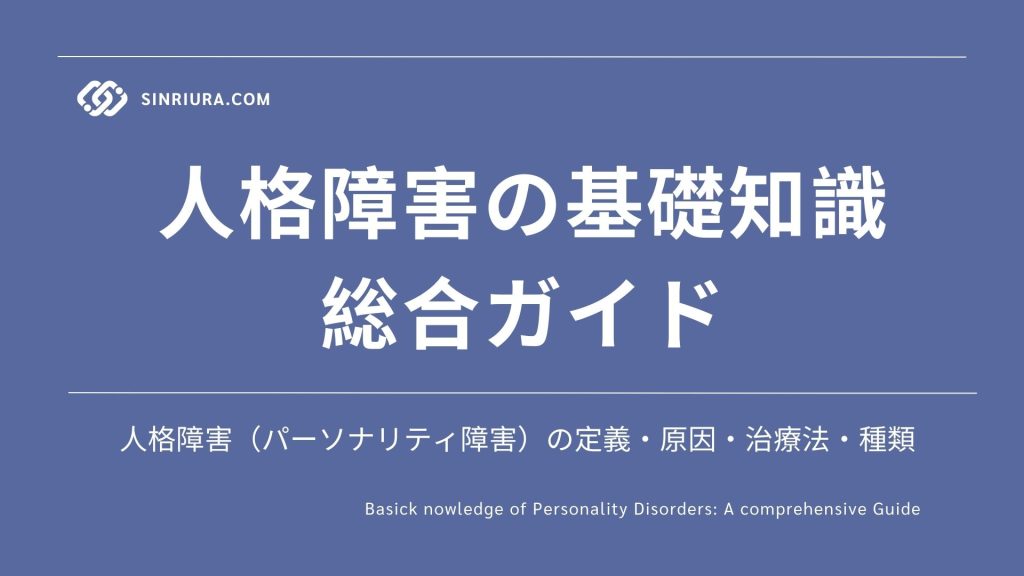
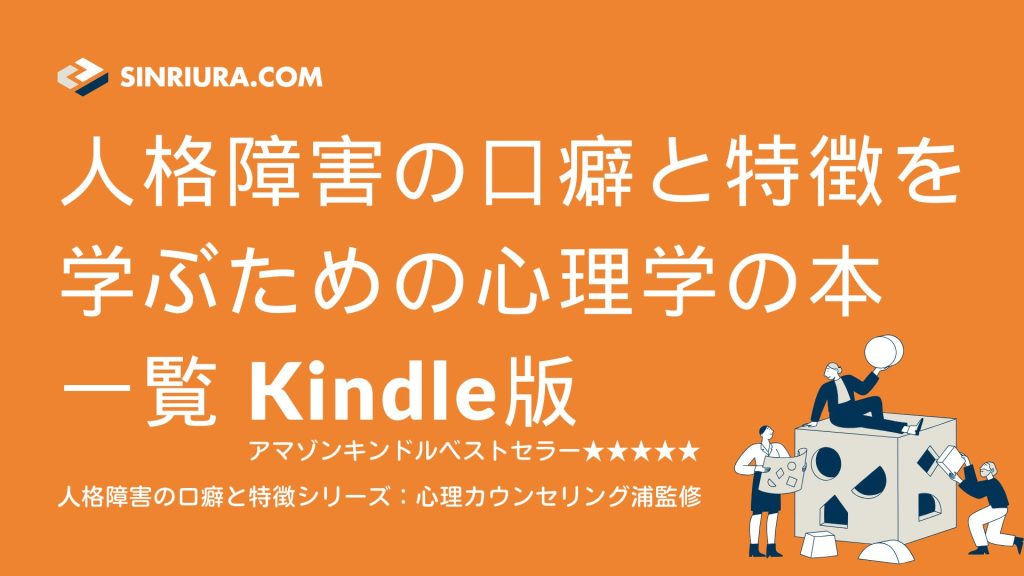
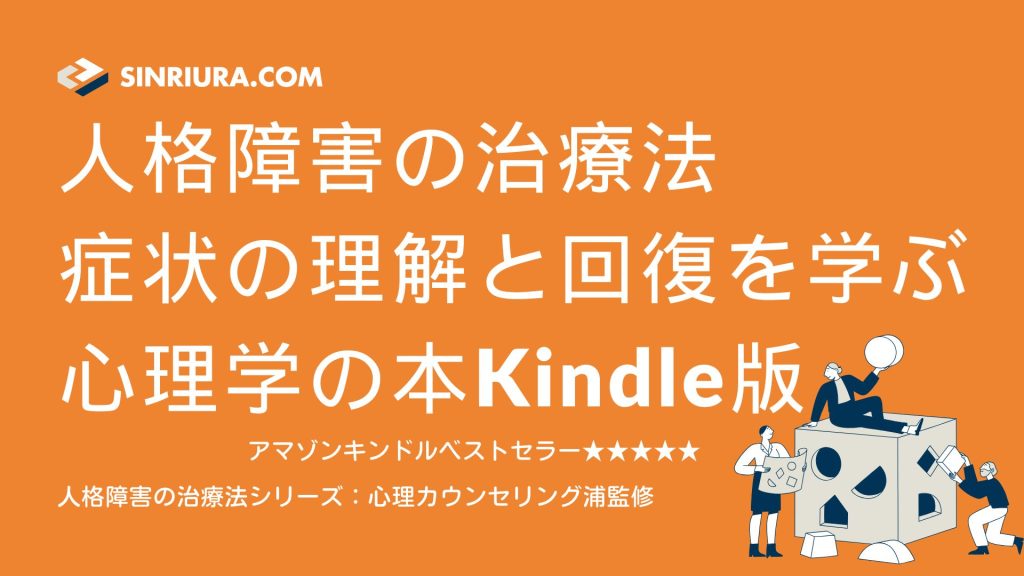
関連する論文・参考文献・URLまとめ
下記は、職場における人格障害(パーソナリティ障害)の特性や対人関係の問題について理解を深めるための代表的な文献やオンラインリソースです。記事中の話題に関連した分野(職場のメンタルヘルス、人格障害の概要、対人スキル、ストレスマネジメントなど)からピックアップしました。
1. 学術文献
-
American Psychiatric Association. (2013).
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.- 人格障害を含む精神障害の診断基準を示す国際的なマニュアル。各パーソナリティ障害の特徴が整理されている。
-
Linehan, M. M. (1993).
Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: The Guilford Press.- 境界性パーソナリティ障害に特化した治療法「DBT(弁証法的行動療法)」の確立者による代表的著書。対人関係や感情調整の問題に関する詳しい解説がある。
-
Gunderson, J. G. (2014).
Handbook of Good Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder. Arlington, VA: American Psychiatric Association Publishing.- 境界性パーソナリティ障害の管理と治療に関する臨床ガイド。仕事場面への応用や周囲の対応策も一部で示唆されている。
-
Millon, T., & Davis, R. D. (1996).
Disorders of Personality: DSM-IV and Beyond (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.- パーソナリティ障害研究の第一人者テオドア・ミロンによる著書。各人格障害の理論的背景や特徴を詳述。
-
Beck, A. T. (1990).
Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York: The Guilford Press.- パーソナリティ障害における認知療法の応用を解説。思考の歪みに着目し、対人トラブルの根本要因を探るヒントが多い。
2. オンラインリソース・機関ウェブサイト
-
国立精神・神経医療研究センター
- https://www.ncnp.go.jp/
- 日本における精神・神経疾患研究の中心的機関。パーソナリティ障害を含むさまざまな精神疾患に関する情報が得られる。
-
厚生労働省:こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
- https://kokoro.mhlw.go.jp/
- 企業や働く個人に向けたメンタルヘルス情報が掲載されている。職場のストレスやハラスメントについての対策・相談先なども紹介。
-
NIMH(アメリカ国立精神衛生研究所)
- https://www.nimh.nih.gov/health/topics/borderline-personality-disorder
- 境界性パーソナリティ障害をはじめ、各種精神疾患の概要や治療法を公的にまとめている。英語リソースだが信頼性が高い。
-
APA(アメリカ心理学会)
- https://www.apa.org/
- 心理学全般の学術情報や最新研究が公開されている。職場のストレスマネジメントや対人スキルに関する記事も充実。
-
Mayo Clinic(メイヨークリニック)
- https://www.mayoclinic.org/
- パーソナリティ障害を含む各種疾患に関する解説、症状や治療法、周囲の対応策などを分かりやすく紹介している。
3. 関連トピックに関する補足
-
職場ハラスメントに関するガイドライン
- 厚生労働省の「職場のパワーハラスメント対策総合サイト」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972_00001.html- 職場でのパワハラ(パワーハラスメント)定義や対策事例、相談先などがまとまっている。
- 厚生労働省の「職場のパワーハラスメント対策総合サイト」:
-
職場メンタルヘルス全般
- EAP(従業員支援プログラム)導入事例などを通じ、人格障害を含む精神疾患のある社員のサポート体制を構築している企業も増えている。早期発見・早期介入が重要。